 |
���ǐ앶���t�H�[�����͉L�����͂��ߑ����̕����������ė���钷�ǐ여���L���Ɉ�ĂĂ��ꂽ���ǐ��ʂ��āA
���������A�f���炵�����ǐ�̕������㐢�Ɍp�����Ă������߂̎s�������̕ł��B
 |
�P�O��̘a�̂Ŏe���Ԃ��Ă��������������̌Í��W�����ғ��퉏�́u�Ëߓ`���̗��v�A
���{�R��Ꝅ�̕��`���˂⏈�Y��A�Ꝅ�̖��c�̌S��x��A����ƂȂ��������铙�̏Љ�ł��B
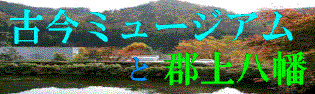 |
�Í��`���̗� |
�ŏ��ɁA��������u�Í��W�v�̌����҂ʼn̐l�ł����铌�����\��̘a�̂��r��œG���ɑ���A��������
�邪�Ԋ҂��ꂽ�e�隬�̂���A�Í��`���̗��t�B�[���h�~���[�W�A���B���ɕ��_���Ꝅ�̍�����Y��ՂƁA
���̋`���ɗR������S��x��ŗL���ȌS�㔪������K��܂����B
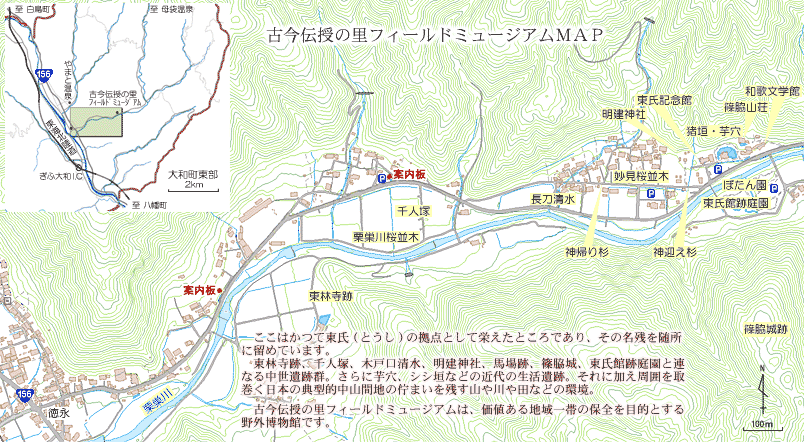 |
|
�����P�T�U������a�����i���瓌�ւQ�����قǂ̌I���쉈���ɂ���܂��B |
 |
| �@�@�@�@�@�@�@�Í��`���̗� �@���������ِՒ뉀��j�Վe����͂��߂Ƃ�����j��Y��������2km�ɋy�ԍL��ȉ����ɓ_�݂����O�����فB �@�����ɂ͘a�̕��w�ق�Z�̐}���ق̂ق��A�t�����`���X�g�����⒃��������܂��B |
|
|
|
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�����ِՒ뉀 |
| �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�̂Ŋ҂����e�� �@���s�ɉ��m�̗����u�����A�S���I�嗐�ɔ��W���钆�A���m��N�i�P�S�U�W�j�㌎�A���R�ɑ�������Z���ē����ւ͑�R�𗦂��ČS��ɐN�����A���R�ɖ������铌�i�Ƃ��j���̋���e����}�P�����B �@���̏�唪�㓌�����͂悭�����������y���A����Q�T�O�N�ɂ��ď��̗���ɋy�B |
| �@�e����̒m�点���́A�����Ŋ֓��ɍݐw���Ă��������i���������j�̒�E�퉏�ɂ����点���B �@�܂肵���S���v�V�̒Ǔ��@�v���c��ł����퉏�A���̔ߕ����ɂ��ĖS���ݐ�������������Ŏ��̈����r�B �@���邪�����Ɂ@�����鐢���݂����@�����肯��@�l�̐̂́@�Ȃ����߂��� �@�����Č��闎��̔߂��݂����߂����̉̂́A�������l�̋���ł��A���������ւ̎��ɂ��������B �@�̋��́@�r�������ā@���܂����v���@�m��ׂ��炸�@�������킯���� �@����ɑ��A���ւ�������������ԉ̂��������B �@���̂���́@�m��ׂȂ��Ƃ��@�̋��Ɂ@������l���@�₷���A��� �@�u������l�v�́A�u�L���̎m�v�̂��ƂŁA���̍����l�i�������B |
|
�L���ِՂ͂悭�ۑ�����Ă��܂� |
|
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�����i���݂����j�� |
�I������z���ē����L�O�ق�
|
�����L�O�� �a�̕��w�� |
|
�����_�� |
|
|
| �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�����_�� �@�����_�Ёi���͖����i�݂傤����j�{�j�́A�e��哌����X�̎��_�������F���P�R���I�ɉ������i�����ӂ��̂��Ɂj���炱�̒n�֊����i���傤�j�����Ɠ`����_�Ђł���A����������������ڂ�������A�_�Ђ����́A���̒n�Ɏc���ꂽ���̂ł���B �@�����āA�����̌�p�҉�������������h�W���������j�������Ă����B �@�����̓������[�ɕ��Ԑ��͐���W�O�O�N�ɋy�ԂƂ����A�ڒʎ��͂V�`�W�����炢�łł���B �@�Ȃ��A�����Ƃ�����Q�R�O���]�̍����́A�e��t�̔n��ՂƂ����Ă���B |
| �@�@���퉏�i�Ƃ��˂��j�Ɣє��@�_�i�������������j�A�̂̔�
�@�Ԑ��菊���_����R���ȁ@�퉏 �@�����N���i�P�S�V�Q�`�V�V�j�e��哌�퉏���A�̎��є��@�_�ɌËߓ`���̐܁A�����{�̎Г��ʼnr���킵���A�̂ł���B |
|
|
|
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�_�}�����R���i����V�O�O�N�]�A�ڒʎ��́@�V���j |
|
|
|
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���q�̐Q�����R���i����T�O�O�N�]�@�ڒʎ��́@�U���j |
| ���q�̐Q���� |
 |
| �\�̉��ڂɂ��肳�������� �@�_�}�����Ɛ_�A�萙�ɋ��܂ꂽ�����_�Љ��Q���A��Q�T�O���ɂ���㏞�Q�O�{�]��̔������R���̎Q���ł��B |
|
�e�隬 |
|
�@�@�@�@�@
�������e��ِ̊� |
���ɂɕ��_���Ꝅ�ɂ䂩��̍�����Y��Ղ̌��w�ƊW����S�㔪����A�S��x��̏Љ�ł��B
| ������Y��� |
�@���S��s��a���@ |
�܂��͂��߂ɁA�S�㔪�������쏈�Y��Ղɗ������܂����B���̏��Y��Ղɂ́A�S��Ꝅ�ɗ����オ��A
���Y���ꂽ�_�������{�����Ε���������܂��B
| �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@������Y��� �@�]�ˎ��ォ�疾���܂ŌY�ꂪ�������ꏊ�ł���B �@�����̓��́A���n���R���ɂ���A���̐�����P�C�Vka�����Y��ɂȂ��Ă����B �@�]�ˎ���A�S��̔_���͊e��̐łɋꂵ��ł����A���l�N�i�P�V�T�S�j���甪�N�i�P�V�T�W�j�ɂ����Đ��ɈꝄ�ɋy�B �@�S���O��_���Ꝅ�̈�ɐ������Ă���u�����v�ł���A�������\�����X���т̂Ƃ��ł������B �@���̍�����́A�S���O�̏W���ꏊ�Ƃ��Ȃ������A���ɎP�A���������A���X�Ƒ�\���]�˂֑���A���đi�E���i�Ȃǒ��i�ɋy�̂ł������B �@���̌��ʁA���{�]�菊�̌������撲�ׂ��č��������o�����B �@�S�����̎��ߏ\�l���A���X�˂͉��ՁA���{�d�b�̏����\�l���]�Ƃ����傫�Ȏ����ƂȂ����B �@�܂��A���߂̂����u�O�J���@�莟�Y�E�����@�l�Y���q��E�������@�R���v�R���̎�́A����N�]�˂��獒����ɓ����B����ԂP�U�l�̔Ԑl��t���A�N���ꂽ�̂ł���B �@�㐢�ɂ����̗���Ԃ߂�ׁA�S��e�n�Ɂu���`����v�����Ă��āA�S��x��̒��́u��������v�̉̎��ɂ��Ȃ��č��ɓ`�����Ă���B �@���̕�W�͕��R�N�ɌY��̋��{���Ƃ��Č�������A�Y��ɂ��������̂������Ɉڐ݂������̂ł���A�Ε��͌S��X��������̎��Ƃ��Č��Ă�ꂽ���̂ł���B�@�@�@�i�S��s�j |
|
���`�����~�x�� |
 |
| �@�@�@�@�@�@�@�@�@�d�v���`�����������@�S�エ�ǂ� �@��R�O��ɂ킽���ėx�葱�����A���~�̂S���Ԃ͓O��ŗx�肠�����܂��B �@�d�v���`�����������Ɏw�肳��A�S���O�喯�x�̂ЂƂɐ������܂��B |
|
�@���R�z���S�L�O�̔��������ꏊ�ɂ���܂� �@�u���{�O�j�v�̒��҂Ƃ��ėL���ȗ��R�z�i�P�V�W�O�`�P�W�R�Q�j�̌S�㗈�K���i�����\�N�i�P�W�Q�R�j�L�O������Ɖ̔�ł���B |
�Ō�ɌS��x��łƔ�����ŗL���Ȕ����������U�܂����B
|
�S�㔪���� |
�ߌ��̌S��Ꝅ�̈���ƂȂ����R���̐ϐ��i���������j��

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�R���ɂ����Ƃ��ē��{��̔��������ւ��S�㔪����i�ϐ���j
�@��������̌���A�i�\��N�i1559�j�퍑����A���������������R�ɏ��z�Â����̂��n�܂�ł���B
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@����ˎ�͒��̊�b����A���͎R����L�̍�
�@����S�㔪���ˎ�͉����c���i�悵�����j�ŁA�鉺���̐����ɗ͂�����āA�_�Ђ̌����⎛�@�̊J��ɂƂ߂��B
| �@�Ă̕������ɂȂ��Ă���S��x��͊e�n�ŗx���Ă����~���ǂ���鉺�ŗx�邱�Ƃ�����ˎ�c�������サ�����Ƃ��n�܂�Ɠ`�����Ă���B�i�c���̖����A�R����L�̍ȂŗL���ȓy���ˎ吳�����܂A����Ƃ��������Ƃ���Ă���j �@�O��ڂ̏�F�́A�������N�i1667�j�A���{�̋��āA�S�㔪����̑�C�z���s�����B�@ �@�Ȃ��A���݂̏�͏��a�O�N�ɑ���ꂽ���̂ŁA��_�邪���f���ł���Ƃ�������A�����̏�̍Č��ł͂Ȃ��悤���B �@���H���c���ɂ͂��鐅�̒��Ƃ��ėL���ł��邪�A������܂��A�O��ˎ��F���������N�i1667�j�A��Ύ��őS�ł��������Ђ����邽�߁A���ʗǐ�̏㗬�R�������琅�������A�S�N������Ŋ������������̂Ƃ����@ �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�ܑ��t�ɐՖڂ��Ȃ��A���ƒf�� �@�P����z���������Ƃ����A�ܑ��t�ɐՖڂ��Ȃ��A���ƒf��ƂȂ����B �@�헤�}�Ԃ���㐳�C���T���œ��邵�A�����Ɍp�������A�O�g�T�R�֓]�����A�S�㔪��������B �@���R�˂�����X�����ɏo�H�̏�R�֓]���ɂȂ��Ă������X�������A���\10�N(1697)�A���R�ׂ̗̌S��˂Ɉ�㎁�̌�C�Ƃ��āA�R���W��̐��ōē]���ɂȂ����B �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���`���Ꝅ�̉��� �@�������A�Q��ڔˎ�E���X����(�����̑�)�ɖ��{�̑t�Җ��𖽂���ꂽ���Ƃ���A�ڑ҂Ȃǂ̂��ߑ����̔�p��K�v�Ƃ��A�S��˂̍������}���Ɉ������Ă������B �@�S��˂͂��̑�Ƃ��āA�N�v�̒������@����Ɓi���傤�߂�j����i���N�Ԃ̎��n�ʂ̕��ρj���������i����݁j����i���N�̎��n�ʂƉB���c�̌��n�j�ɉ��߂����A�����s���Ƃ��ĕS���Ꝅ���N�����̂ł���B�@ �@�����ƌĂꂽ�A���S�N(1754)����S�N�������Ꝅ�ł���B �@�Ꝅ�͌S��ɗ��܂炸�A�S��˗a����V�̂ɂ��L����A�Ō�͖��t�̋^�������ɔ��W���čs�����B �@�Ꝅ�̒��S�͌S��ł�����������Y�҂̃��X�g������ƁA���̑��̒n������S���A����i�����̓��C�Ǒ����Ђ�������ނ�j�̑P�E�q��ƒ��������đi���s�����߂Ŏ��߂ɂȂ��Ă���B �@�Ꝅ���͍]�˂ɏo�ĉ��đi�┠�i�Ȃǂői���A���W�N�P�Q���A�]�菊�ٌ̍��̌��ʁA���X�Ƃ͉��Ղ��A���ƒf��B�@�X�ɁA���t�ł���V���{���������͂��߁A��N��A�����s�A���Z�S��Ȃǂ���Ƃ��ꂽ�̂ł���B �@����N�i1759�j�A�R�K�����ˎ�Ƃ��ē��邵�A���̌�͎���ɂ킽��S������߁A�����Ȃ����ɖ����ېV���}���Ă���B�@���݂̏�͏��a�W�N�ɍČ����ꂽ���̂ł��B |
�@
|
�@�ˍZ�@�����ِ� |
|
�_�_��t �@�����A�s���ёg�̕x���荶�q����̗���������ꏄ�炪�A�������ĂȂ���������ɖ�t�@����u���ė����������B �@�V�����N�i�P�V�W�P�j���̖�t�@���n�̒|�ѓ��Ɉ��u��������B �@���̌�A�R�Q�T�]���̐_�_�u����ɂ��A���a�S�N�P����t�@�������炢�����A���N�V���̔n�s�𗘗p���A���ތA�ɕ�҂��āA���Ŏ����s�����B �@�Ȃ��A�_�_��t�́A�����ɐ��̊O�A���a�A�����������ƌ����`�����āA�����̐l�X���M����Ă���B �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@(���n�������j |
|
|
|
|
|
�����포�a |
 |
|
�@�@�@�@�@�@�@�S�㔪���̖��͂��y�����W�� �@�@�@�@�@�@�@�@�@�S�㔪�������� |
|
|
|
|
|
�@�_�� �@�����̖����ƌ����Ă��܂����ꎞ�A�����p���ɉ������ꂽ���Ƃ�����܂��B �@�A�̎t�E�@�_�i�P�S�Q�P�`�P�T�O�Q�j�ɗR�����閼�ł���B �@�@�_�͌Í��`���̋�㓌�퉏�i�Ƃ��˂�聁��X�̓��ɗD��A�����ȉ̐l�ł���ƂƂ��Ɍ��o�����̊w�҂ŁA�u�ËߏW�v�����̑��l�ҁj�Ɏt��������������̘A�̎t�ł���B |
|
|
|
|
|
���h���Ɨ����� |
�삯���̒T�K�ł�������x�U��邱�Ƃ������߂��܂��B