|
|
平成21年3月12日 |
岐阜県垂井の南宮大社の南宮山(419m)に登山して、大社にお参りのあと赤坂の金生山明星輪寺(通称
虚空蔵菩薩)にお参りし、奇岩で有名な金生岩巣公園巡りをして、谷汲山華厳寺のご開帳も参拝した忙しい1日を紹介します。
|
|
平成21年3月12日 |
|
南宮大社参拝 |
| 美濃国府の南にあるので「南宮」 南宮大社の祭神は、鉱山・金山など、鉱物をつかさどる金山彦大神(カナヤマヒコノオホカミ)です。このこともあって『延喜式』には「仲山金山彦神社」として記載されています。南宮大社と呼ばれるようになったのは、美濃国府が北方に設けられてからで、「国府の南の宮=南宮」という意味からきた名称でした。 |
|
御神体の「南宮山」へはこの門から登ります |
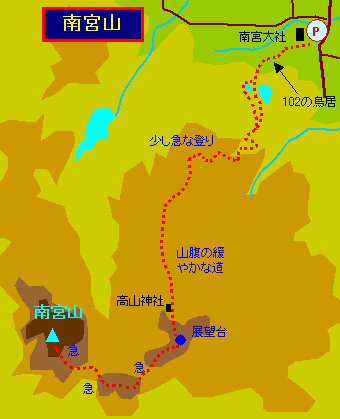 |
|
南宮山登山ルート |
|
南宮山登山 |
|
南宮山には椿が多く、また奉納されるので敷地内には椿の森もあり、別名「椿大社」とも呼ばれます。 |
|
|
蛇溜池の横に関ヶ原合戦の時の安国寺恵瓊陣跡があります。
|
安国寺恵瓊陣跡 |
| 安国寺恵瓊 安芸の守護武田氏の遺児といわれています。 武田氏滅亡の後、安芸安国寺で出家しました。 毛利氏の外交僧として活躍し、豊臣秀吉の才能を見抜いた話は有名です。 関ヶ原合戦では石田三成らと共謀して毛利輝元を西軍の総大将に引き込むことに成功しました。 合戦の当日は南宮山のふもとに陣を構えましたが、吉川広家の裏切りで動くことができず敗戦後逃亡、京都に潜んでいるところを捕まり六条河原で斬首されました。(垂井町教育委員会) |
安国寺恵瓊陣跡のすぐ近くに市杵島(いちきしま)大神の祠があります。
|
市杵島大神 |
| 市杵島(いちきしま)大神 素盞鳴尊と天照大神が、天安河で誓約をした時に化生した神様で、島に斎く女神です。 なぜここに祀られているかは分かりません。 |
市杵島大神を過ぎた辺りから山道となります。
20分ほど登ると展望台へ到着します。
|
展望台 |
|
展望台には望遠鏡があり(無料)名古屋駅前のビル群や安八の木曽三川公園の展望塔など手に取るように見えます。 |
|
|
 |
|
記念写真 |
 |
|
毛利秀元陣跡 中国百二十万石の太守である毛利輝元の養子。 関ヶ原合戦では西軍に参戦した輝元の名代で南宮山に陣を構えたましたが、東軍に内通した一族の吉川広家に押し止められ、合戦に参戦できませんでした。 その際、進退に窮した秀元が、摩下に兵糧を使う真似をさせた話は、「宰相殿からの弁当」として知られています。 その後、大坂城に戻った秀元は、籠城し徹底抗戦すること主張しましたが聞き入れられず、毛利家は大幅に減封されてしまいました。 (垂井町教育委員会) |
| この陣形図を見ると徳川家康は小早川・吉川などの裏切りがなかったら完全に袋のネズミだった |
展望台から深い谷に下り、再び途中の山に登り、もう一度谷へ下り南宮山山頂へ
|
目の前に南宮山が見えていても谷へ下ります。 |
南宮山山頂は見通しが悪く展望のいい画像はありません
|
南宮山山頂 |
 |
 |
|
山頂は二等三角点 |
|
南宮山からの帰りは途中から西側の道を辿ります
|
高山神社 |
| 高山神社 祭神 木花咲耶姫命(このはなさくやひめのみこと) 南宮山は、古く不破山、美濃のお山、美濃の中山とも呼ばれ、この奥宮は、椿姫宮とも言われてきました。 美濃国の水源を司る女神として御神徳の高い神様です 子安神社 祭神 保 食 神(うけもちのかみ) 山頂の神様は、稲を育てる水の神様です。 この神様は安産、子育ての霊験高く、全国の子安神で、最初に従五位下の神位に預かられた有名な神様です (垂井町) |
更に下ると「眠神」があります
|
眠神と薬師堂跡 |
|
眠り神の由来 |
|
|
南宮大社境内へ戻り次は赤坂へ
次は赤坂の虚空蔵菩薩(金生山明星輪寺)へ
|
金生山明星輪寺 |
|
平日のためか参拝客も少なく閑散としています。 |
| 岐阜県指定天然記念物金生山の陸貝と生息地 陸貝とは、陸生の貝類のことであり、殻を作るために多くのカルシウムを必要とすることから、良質の石灰岩で形成されている金生山は日本屈指の生息地となっています。 陸貝は非常に行動範囲が狭いため、その地域固有の種が群生し、金生山においても、クロダアツクチムシオイやオルサトギセルのような他所では発見されていないものを含め、ミカドギセル、イブキゴマガイなど約40種類が確認されています。 (大垣市教育委員会) |
| 金生山明星輪寺由来 持統天皇の勅願により鎮護国家の道場として朱鳥元年(686)役の小角の創建にかかり七堂伽藍を始め一山五坊を創建し本尊虚空蔵菩薩を安置す。 その後衰退していたが空海(弘法大師)来山し諸堂を再建す、このとき桓武天皇は勅願を下し封戸三百石を寄進された 久安四年(1148)雷火の為に伽藍は残らず焼失したが時の住僧は八方手を尽くし復興を図る。 その後慶長十四年(1609)美濃高須の城主徳永法印壽昌は本堂を初め諸堂を再建された。 江戸時代には入って大垣藩主戸田家は代々祈願所と定め帰依し保護す、 明冶維新以降は新時代信仰の対象として広く一般の参詣者を迎え法灯を今日に伝えている。 |
|
本殿の奥は岩屋になっています |
|
眺望は天下一 遠く金華山まで見えます |
|
奥の院は巨岩の下 一般人もお参りができますので是非奥まで入ってお参りしてください |
|
|
|
金生山岩巣公園 |
|
ダイエット検査通路みたいな通り道が各所にありますが白い石が敷いてあるので道は迷いません |
|
|
|
|
丁度 谷汲山華厳寺のご本尊のご開帳が五十四年ぶりに行なわれているのでお参りすることにしました。
|
谷汲山華厳寺 |
| 西国三十三所観音霊場の結願・満願霊場 豊然上人によって延暦十七年(798)にて草創されてより醍醐天皇、朱雀天皇、花山法皇、後白河法皇を始めとする皇室、朝廷からの帰依厚く、いにしえより観音信仰の霊験あらたかな美濃の名刹として1200年に渡って絶え間ない信仰を集めてきました。 また当山は日本最古の観音霊場である「西国三十三所観音霊場」の第三十三番札所で結願・満願霊場としても知られ、春には桜、秋には紅葉の名所として賑わいをみせています。 |
| 五十四年ぶりに御開帳 西国三十三番満願霊場の谷汲山華厳寺では、平成21年3月1日(日)から14日間にわたりまして、秘仏である御本尊の十一面観世音菩薩を昭和30年以来となります54年ぶりに御開帳致します。 |
| 精進落としの鯉 正面向拝の左右の柱には「精進落としの鯉」と称する、銅製の鯉が打ち付けられている。西国札所巡礼を三十三番札所の当寺で満願した者は、その記念にこの鯉に触れるならわしがある。 |
|
ご本尊から「白い綱」と呼ばれる紐が3本 |