|
|
遊歩クラブ21主催 行き先 平成21年4月9日 |
尾根道に、吹き上げる風、足すくむ H,O
|
|
遊歩クラブ21主催 行き先 平成21年4月9日 |
遊歩クラブ21主催による福井県今庄町のかたくりの里と源平の古戦場の燧ヶ城跡・藤倉山・鍋倉山の春山登山と
観道山弘法寺
八十八ヶ所巡りの散策を楽しんできました。
JR今庄駅前を出発して燧ヶ城跡(ひうちが)・藤倉山・鍋倉山・八十八ヶ所登山をご案内します
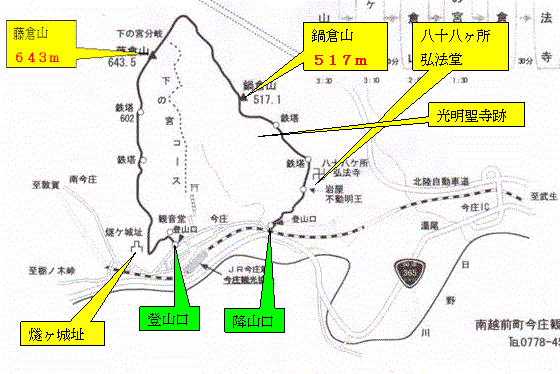 |
|
高度差約500m、歩行時間3.5〜4時間 |
| 今庄の宿場を守るように聳えている藤倉山(643メートル)と鍋倉山(516メートル)。 両山の山麓には七堂伽藍(しちどうからん)と千坊があったと言われ、谷間一帯はブナの樹林が繁茂し、懸崖に散在する多くの巨石は古代の岩座(いわくら)であったと推測されます。 このような今庄の立地を利用して建てられた木曽義仲の城跡は、今も平家軍との戦いの跡を忍ばせています。 標高1099メートルの山頂にある夜叉ケ池(やしゃがいけ)は竜神夜叉にまつわる数種の伝説とともに雨乞いの池と言われ、夜叉渓谷には緑の合間を縫うように豊かな水が流れています。 町ではハイキングコースやキャンプ場を整備しており、山菜とり、渓流釣り等、四季折々訪れる人が歴史遺産を散策しながら、豊かな自然を楽しむことができます。 |
|
藤倉山・鍋倉山はJR駅前から始まります。 |
 |
|
JR今庄駅前から見た左から、燧ヶ城跡(269m)、藤倉山(643m)、鍋倉山(516m)のピーク |

駅前商店街の道を西へ入り突き当りを左(南)へ曲がります。
50mほど進むと御札場跡の杭標識のある空き地の前を通ります。
|
今庄宿高札場跡 |
 |
|
|
高札場跡(高野家六家) |
|
空き地の南側が御札場跡の案内板のある家の前を通ります。
|
今庄宿御札場跡 |
 |
| 御札場跡(北村善六家) 福井藩第四代藩主光通(みつゆき)の時の寛文元年(1661)十一月、福井藩がはじめて幕府から銀兌換の藩札発行が認められた。 福井藩内では藩札の使用が強制されたので、藩の南端の大宿場町である今庄では、旅人や商人が金銀を藩札に、あるいは藩札を金銀に両替するために御札場が設けられた。 今庄宿では最初北村大平家が、その後北村新平家が、つづいて西尾茂左衛門家が、その後享保十五年(1730)からは当北村善六家が勤めた。 (今庄町教育委員会) |
そのまま100mほど進むと西側に「燧ヶ城址」の大きな説明板があります。
この前の路地を西へ入ります。
|
|
|
街中は宿場町らしく静かなたたずまいです。 |
|
この説明板の前の路地を西へ入ります。 |
|
|

正面に「新羅神社」が見えてきますが南へ入ると「燧ヶ城址登山口」の石碑があります。
| 燧(ひうち)ヶ城址へ 旧街道沿いにある新羅神社・観音堂の脇からへの登城道が通じています。 登ること約20分、低い石垣が積まれた虎口に至ります。 |
|
かたくりの里 |
 |
| 観音堂の上り口には標識があります |
50mほど登ると「からくりの花」の群生地へ出ます。
 |
|
しばらく登ると一面の「かたくりの花」に出会えます。 |
|
|
 |
|
白いかたくりの花が人気でした |
 |
途中途中に「燧ヶ城址」の案内石碑があります。
 |
| 燧ヶ城の歴史 燧ヶ城の築城は古く源平の合戦の頃にまでさかのぼる。 寿永2年、木曾義仲は追討の平家の軍勢を迎え撃つため、仁科守弘らに命じて、燧ヶ城を築かせたのがはじまり。 源平盛衰記に「北陸道第一の城郭」と記されたこの城は、交通の要衝を押さえた城であったため、時代を経てもこの城を舞台に戦がくり広げられました。 天正三年には、下間頼照ら一向一揆勢が立て籠もり織田信長と戦い、次いで天正11年の賤ヶ岳の合戦の折りには、主将柴田勝家自らがここを守ったなど我々の歴史物語にも聞き覚えがあります。 |
 |
登山口から20分ほどで燧ヶ城址に着きます。
|
燧ヶ城址 |
 |
| 土塁や石垣等の遺構があちこちにあります。 |
 |
|
寿永2年(1183)木曽義仲が築城 |
 |
| 燧ヶ城の木曽義仲と平家の戦い 平家物語や源平盛衰記などでよく知られている燧ヶ城(海抜270m)の下には、鹿蒜川沿いにに、木の芽峠へ通じる北陸道と、山中峠への道筋、更に日野川と平行して栃の木峠へ通じる北国街道がいずれも、この麓で交わる。 すぐ近くの杣山(そまやま)城と敦賀金ヶ崎城とともに、この城は北陸の関門を制する重要な場所であった。 『源平盛衰記』によると、寿永二年(1183)四月、平家は木曽義仲追討のため、平維盛の率いる十万の大軍を北陸路へ差し向けた。 義仲は越後の国府にいて、燧ヶ城には仁科太郎守弘や、平泉寺長吏斎明威儀師(ちょうりさいいぎし)を大将として立て籠もり、日野川を堰き止めて周囲一帯を水浸しにして平家の大軍を迎えた。 しかし『北陸道第一の城郭なり』といわれた燧ヶ城も斎明威儀師が平家に内通するに及んで、たちまち陥落し、義仲軍は敗走した。 その後五月の倶利伽羅峠の合戦に義仲は勝利し、七月には上洛した。 南北朝時代に入ると、再びこの城は攻防の戦場となり、延元元年(1336)には、今庄入道浄慶(じょうけい)が足利方の将として立て籠もり、南朝方の新田義貞軍に味方して挙兵した杣山(そまやま)城の瓜生保軍と対抗、敦賀金ヶ崎との連携を絶つ作戦に出た。 『太平記』では、新田義貞、脇屋義助らの行軍に際し、由良光氏(ゆらみつうじ)の節義に感動した浄慶が金ヶ崎への道を開いたというエピソードが記されている。 戦国時代の天正三年(1575)には越前一向一揆の総大将下間筑後法橋頼照(しもまちくごほうきょうらいしょう)が藤島超勝寺、荒川興行寺の一揆と立て籠もり、信長軍と対戦したと伝えられている。 このようにこの燧ヶ城は数世紀にわたり戦略上の重要な拠点として利用されてきた。 なお現在残っている土塁・石垣等は戦国時代末期のものである。 幾多の戦いの地、燧ヶ城址は現在も憩いの広場として、また、今庄の街並が一望できるハイキングコースとして町民に親しまれている。(今庄町教育委員会) |
 |
続いて藤倉山へ向かいます。
|
戦国時代の歴史を思わせる今庄宿が眼下に広がります。 |
「燧ヶ城址」から70分ほどで藤倉山山頂へ着きます。
|
藤倉山 |
|
かたくりの里から途中のところどころに標識があります |
|
山頂らしくない山頂 |
 |
|
北国街道などが一望できるマイクロウエーブ無線の反射板の脚元で、昼食! |
 |
|
鍋倉山 日野山 |

|
|
藤倉山山頂よりの展望 日野山、遠くは白山まで展望できる |
 |
|
はいチーズ |
腹ごしらえが出来たら、つづいて鍋倉山へ向かいます。
|
引き続き鍋倉山へ向かいます |
藤倉山から70分ほどで鍋倉山の山頂の目印「三叉路の標識」に着きます。
|
鍋倉山 |
|
鍋倉山の山頂も平です |
|
八十八ヶ所目指して下山です |
 |
|
鍋倉山より望む弘法寺八十八ヶ所 |
次は観道山弘法寺 八十八ヶ所目指して下ります。
|
途中「イワウチワ(岩団扇)」(葉が団扇に似ているから)の花が登山道脇に綺麗に咲いていました。 |
|
白い「イワウチワ」 |
鍋倉山から観道山弘法寺へは30分の行程です。
|
観道山弘法寺 八十八ヶ所 |
|
鍋倉山山頂から30分ほどで観道山弘法寺に到着します |
|
境内を通って下山します |
|
極楽橋 |
|
岩屋不動明王様 |
|
最初のお地蔵様から九十九折れの道を下ります。 |
観道山弘法寺から八十八ヶ所のお地蔵様を拝みながら九十九折れの道を下ります。
段差の高い登山道は下りのほうが疲れます。
|
途中とちゅうに八十八の祠があります |
|
八十八のお地蔵様を巡ると登山口へ到着します |
弘法堂から駐車場まで約20分。この区間が一番は疲れました。
|
一行はくたくたです。途中「やすらぎ温泉」で汗を流して帰路につきます |
やすらぎ温泉は今庄365スキー場に隣接しています。
 |
今庄365温泉 やすらぎ [立ち寄り温泉 今庄365スキー場内の温泉施設。 |
(皆さんお疲れ様でした)
カタクリの、花咲き乱れ、人騒ぐ S,H